「ママ、抱っこ〜!」
毎日のようにせがまれて、正直くたびれることはありませんか?
「甘えすぎかな?」「このままでいいのかな?」と迷うこともありますよね。
そもそも、どうして子どもはそんなに“抱っこ”が好きなのでしょうか?
でも実は、その一言には子どもの“大切な心のサイン”が隠されているんです。
「また抱っこ?」の裏にある子どものホンネ
「抱っこして」という言葉には、子どもの心からの想いが込められています。
ただの甘えではなく、
- 「安心したい」
- 「つながりたい」
という大切なメッセージなのです。
幼稚園で発見!抱っこの行列が生まれたワケ
ある日、娘の幼稚園に用事で立ち寄ったときのこと。
ふとした瞬間に、園児たちから「抱っこして〜!」と声が上がりました。
最初に飛び込んできたのは、娘のクラスのお友だち。
思わず「いいよ〜!」と抱っこすると、その様子を見ていた娘も「わたしも〜!」とおねだり。
気がつけば、次から次へと子どもたちが私の周りにわらわら集まってきました。
「抱っこ〜!」「わたしも〜!」と声が重なり、あたりはもう大混乱。
すると娘がひと言。
「抱っこしてほしい人、ならんで〜!」
その瞬間、子どもたちは今度はきれいに整列。
まるでアトラクションの順番待ちのように、一人ひとり抱っこを楽しんでいました。
ぎこちない抱っこは「もっと安心したい」の合図
抱っこの行列に応じているとき、ふと気づいたことがありました。
それは、抱っこに慣れていない子の存在です。
身体がまっすぐのままで力を抜けなかったり、しがみつき方がぎこちなかったり…。
そんな姿から「この子はまだ“身をゆだねる”経験が少ないのかもしれない」と感じました。
実は、抱っこの時間の積み重ねは、子どもが「安心して甘えられる力」を育てる大切な土台。
ぎこちなさの裏には、
- もっと安心したい
- ぬくもりを感じたい
そんな小さなサインが隠れているのです。
ママじゃなくてもいい!?子どもが求めているのは“ぬくもり”
驚いたのは、私のことを「○○ちゃんのママ」としか知らない子まで、迷いなく「抱っこ〜!」とやって来たことです。
その瞬間、気づきました。
子どもにとって大切なのは「誰のママか」ではなく、「あたたかいぬくもり」そのもの。
つまり、求めているのは“人”ではなく“安心感”なのです。
考えてみれば、大人でも同じですよね。
安心できる人の声や、そっと寄り添ってくれる手のぬくもりに救われた経験はありませんか?
子どもにとって抱っこは、それと同じ“心を落ち着ける場所”なのだと思います。
実際、私の娘もときどき友人や親せきに「抱っこ〜!」とせがみます。
親じゃなくても、抱きしめてもらうだけで心はちゃんと満たされるのです。
むしろいろんな大人に受けとめてもらえることは、子どもにとって「世界は安心できる場所」という信頼を育てる時間になるのかもしれません。
抱っこから読みとれる4つの心のサイン
抱っこの時間を通して、子どもの心の声が見えてきます。
よく観察すると、こんなサインが隠れているのです。
- 安心したいサイン
→ 「ママに守られている」と感じたいときに出る言葉。 - つながりたいサイン
→ ぎゅっと抱きしめることで、心と心が近づく体験に。 - 経験不足のサイン
→ ぎこちない抱っこは「身をゆだねる練習中」かもしれません。 - 愛されている証のサイン
→ 抱っこを独り占めしなくても平気な子は、すでに安心感を持っている証拠。
Q&A:毎日せがまれる抱っこ、どう応える?
Q1:毎日の抱っこに疲れてしまいます…。全部応じるべき?
A:無理のない範囲で大丈夫です。「ちょっとだけね」「あとでね」と伝えることも子どもにとって大切な経験。全部応じるよりも「安心できる抱っこの時間」を持てているかどうかが大事です。
Q2:抱っこばかりで、甘えん坊にならないか心配です。
A:抱っこは「甘え」ではなく「安心のサイン」。たっぷり安心を感じた子どもは、やがて自分から少しずつ離れていきます。安心が自立への一番の近道です。
Q3:下の子がいて、抱っこしてあげられないときは?
A:すぐに抱っこできなくても大丈夫。「あとでね」と約束したり、代わりに手をつなぐ・頭をなでるなど、短いスキンシップでも心は満たされます。
抱っこは小さなSOS。受けとめ方しだいで心は育つ
「抱っこして」という言葉は、子どもからの小さなSOSであり、大切な愛情のリクエスト。
大変に感じる日もありますが、その時間は子どもの心を支え、同時に親の心もあたたかくしてくれる瞬間です。
抱っこをすべて完璧に応じる必要はありません。
でも「子どもが安心できる時間を意識的につくる」ことで、抱っこはかけがえのない心の栄養になります。
今日も、あなたとお子さんの抱っこの時間が、あたたかい思い出として心に残りますように。

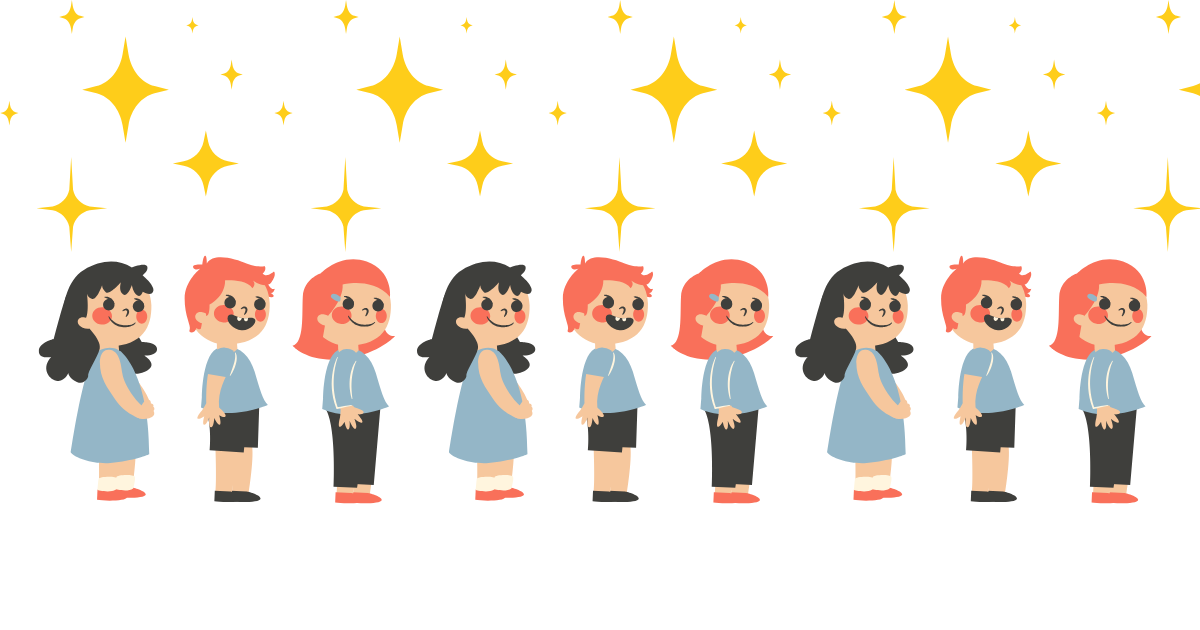


コメント